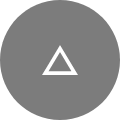OECC技術・広報部会では、若手職員の育成と会員間ネットワークの強化を目的に、海外環境調査ミッションを継続的に実施しています。
令和7年度の訪問先は、アジアの気候変動対策を先導する都市、タイ・バンコク。5月25日から31日にかけて、政府機関や国際機関、研究機関、都市行政、さらには現地の環境関連施設を訪問し、各分野の専門家と活発な議論を交わしました。
会員企業や研究者、事務局職員を含む約12名が参加し、1週間にわたる濃密なプログラムとなりました。
<概要スケジュール>
| 05/25(日) |
|
| 05/26(月) |
|
| 05/27(火) |
|
| 05/28(水) |
|
| 05/29(木) |
|
| 05/30(金) |
|
| 05/31(土) |
|
タイ天然資源環境省 環境気候変動局(DCCE)
DCCE(Department of Climate Change and Environment)は、2023年に新設された気候変動政策の司令塔です。NDC(国別削減目標)の進捗管理や、NAP(国家適応計画)の策定と実施、国際交渉や自治体支援まで、気候変動に関わるあらゆる政策を一元的に担当しています。
今回の意見交換では、担当官より現在国会提出に向けて調整が進む「気候変動法案」の概要が説明されました。法案には排出量取引制度(ETS)やカーボン税、さらには「気候変動基金」の創設が盛り込まれており、閣議承認を目前に控えた段階にあるとのことでした。
参加者からは、制度導入による産業界・市民への影響や、地方自治体の実行体制について質問があり、DCCE側からは「段階的な導入と透明性の確保が不可欠」との回答がありました。
また、DCCEが自治体向けに開発している「気候リスクマップ」も紹介されました。洪水、干ばつ、熱波など地域ごとに異なる気候リスクを可視化し、地方行動計画の策定を支援するもので、日本の防災・適応計画との比較議論も行われました。
さらに、ゼロエミッション実現に向けた重点技術として、CCUS(炭素回収・利用・貯留)、再生可能エネルギーの導入、EVの普及状況や課題が紹介され、参加者からは「地域に根差した適応策と産業政策をどう統合するかが今後の鍵」との意見が出されました。

地球環境戦略研究機関(IGES)バンコク事務所
IGESバンコクセンターは、アジア太平洋地域を対象に持続可能な政策形成を支援する拠点であり、UNFCCCと協働してRCC-AP(Regional Collaboration Centre for Asia-Pacific)を運営しています。これを通じ、40か国以上の途上国に対してNDC支援や炭素市場整備、キャパシティ・ビルディングを行っています。
意見交換では、ASEAN諸国間の政策調和の難しさが話題となりました。たとえば、廃棄物分野では拡大生産者責任(EPR)をすでに導入している国もあれば、まだ検討段階の国もあり、地域全体での足並みを揃えることは容易ではないとの指摘がありました。
参加者からは、日本の自治体が長年培ってきた廃棄物分別やリサイクル推進の経験が、ASEAN各国の段階的導入の参考になるとの意見がありました。
また、IGES職員からは、適応分野での資金アクセスの難しさも共有されました。GCF(緑の気候基金)に提案しても採択されにくい背景として、「行政内部での調整不足」「専門人材の不足」「外部コンサルへの過度な依存」などの課題が挙げられました。
参加者からは「提案書作成に携わる人材をどう育成し、組織内で継続させるかが鍵」との意見が出され、双方で共通の課題意識を確認しました。

バンコク都庁(BMA)
バンコク都庁は、2050年までのネットゼロ実現を目標に掲げ、交通、廃棄物、エネルギー、都市緑化など多方面で施策を展開しています。
今回の訪問では、家庭や事業者が排出量に応じて料金を支払う「廃棄物分別制度(PAYT)」の導入が紹介されました。市民の行動変容を促す経済的インセンティブとして注目されています。
また、深刻化するPM2.5問題への対応として、市内70か所に設置されたモニタリングステーションによるリアルタイム監視や、専用アプリ「AirBKK」を活用した市民への警報通知システムが紹介されました。
「市民の信頼をどのように得ているのか」という質問に対して、BMA職員は「データ公開の透明性とSNSを通じた継続的な情報発信が鍵」と回答。市民参加を重視した取組姿勢が印象的でした。
さらに、食品廃棄物の再利用や、使用済み電池の回収にポイントを付与するアプリなど、デジタル技術を活用したユニークな廃棄物管理の仕組みも紹介されました。

BMAの取組み現地視察① Benchakitti森林公園
バンコク中心部に位置するBenchakitti森林公園は、旧タイたばこ公社の跡地を再開発して誕生した広大な都市公園です。24ヘクタールの敷地に人工池や湿地、水路が配置され、雨水調整や浄化機能を備えた多層的な水循環システムが整備されています。パークレンジャーによる説明では、ゲリラ豪雨による洪水リスクを軽減しながら、生態系を再生する仕組みが詳しく紹介されました。
参加者はバギーで園内を巡り、在来植物や野鳥の観察を行いながら、都市再開発と自然再生を両立させるデザイン思想を学びました。市民参加型の生物多様性モニタリングには「eBird」アプリが活用されており、今後は公園内でのホタルの再生も目指しているとのことでした。

BMAの取組み現地視察② Nong Khaem廃棄物処理場
市内最大規模のNong Khaem廃棄物処理施設では、焼却、たい肥化、感染性廃棄物処理、衛生埋立などが一体的に管理されています。
視察では、既存の焼却炉(処理能力300トン/日)に加え、2026年に稼働予定の新焼却施設(処理能力1,000トン/日)の計画概要が紹介されました。
特に注目されたのは、ドイツ製の膜生物反応器(MBR)と逆浸透膜を用いた浸出水処理設備で、1日700m³の汚水を再利用可能な水に浄化しています。この処理水は場内清掃や緑地散水にも利用されており、参加者からは「高度な処理技術が地域住民の理解を得るうえでも重要」との意見がありました。

BMAの取組み現地視察③ Bang Khun Thien地区(マングローブ植林事業)
バンコクで唯一海に面するBang Khun Thien地区は、過去数十年間で海岸線が4〜6km後退するなど、深刻な海岸侵食に直面しています。視察では、資料館で地域の歴史や環境変遷について説明を受けた後、ボートで現地を巡回。海岸沿いに整然と並ぶ竹製の波消し堤防と、背後で育つマングローブ林の姿が印象的でした。この取組により土砂が堆積し、沿岸生態系の再生が進んでいます。かつて人が暮らしていた集落が現在では海中に沈んでいる光景も確認し、気候変動の影響の大きさを実感しました。
地域住民や学校、NGOも積極的に植林活動に参加しており、行政による構造物整備と地域参加型の自然再生を組み合わせた「ハイブリッド型沿岸防災モデル」として、国際的にも高い注目を集めています。

フォトギャラリー
 |
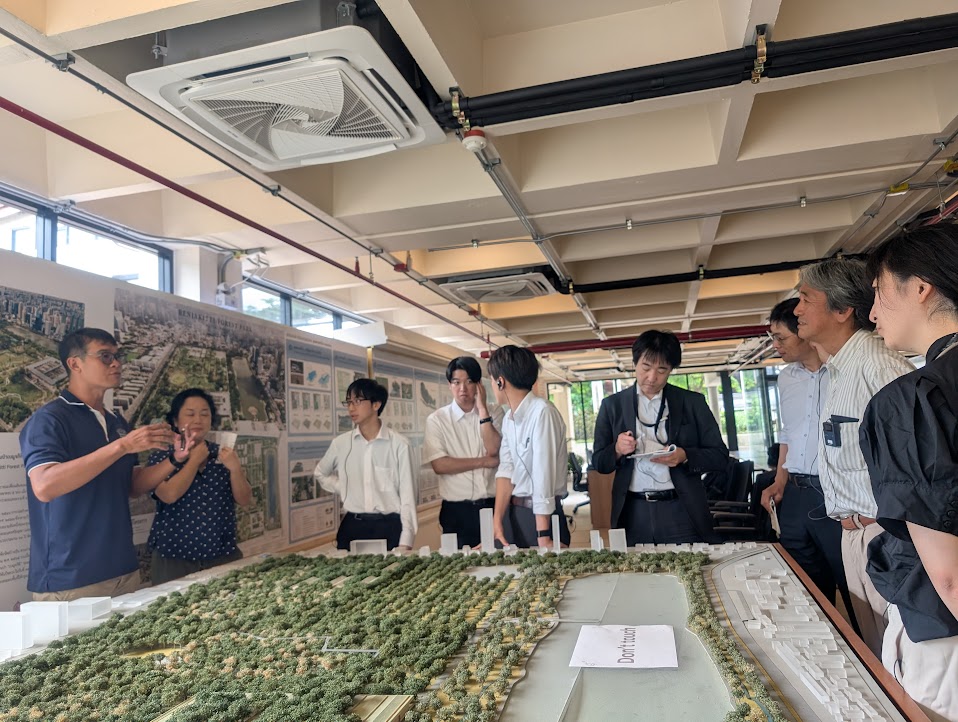 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
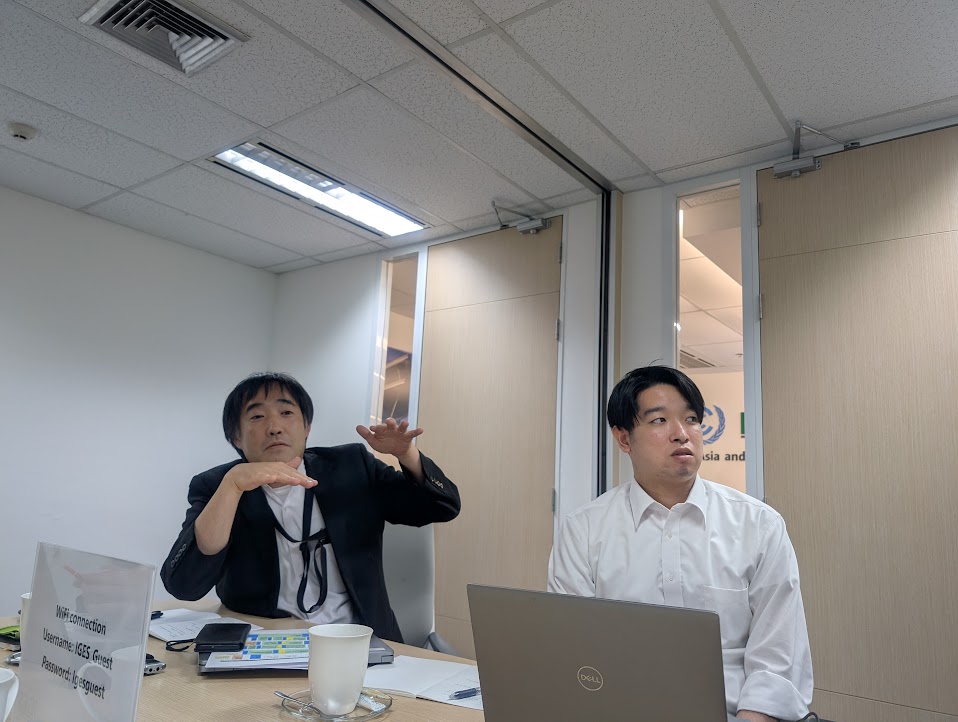 |