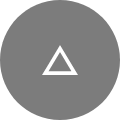理事長メッセージMESSAGE

一般社団法人「海外環境協力センター」(OECC)は、気候変動対策や資源循環に加え、生物多様性保全など国際社会が直面する地球環境問題への対応や持続可能な社会形成に向けた海外環境開発協力分野において幅広い活動を展開しています。またOECCは、これまでの活動を通じて育んできた国内外のネットワークをフル活用することにより、「環境インフラ海外展開プラットフォーム」(JPRSI) や「フルオロカーボン・イニシアティブ」(IFL)の事務局としての役割を担うなど我が国の国際的な取組に貢献しています。
昨年11月アゼルバイジャンの首都バクーにて開催された気候変動枠組条約COP29では、パリ協定第6条に基づく炭素市場ルールが最終合意に至り、また気候資金に関し、「2035年までに少なくとも年間3,000億ドルを官民その他の多様な資金源から動員する」との世界目標が合意されました。さらに、私自身参加したサイドイベントでは、気候変動対策を進めるうえで重要な役割を果たす都市と国の機関との連携について更なる強化に向けた議論が展開されました。
他方、2024年の世界平均気温の産業革命前からの上昇幅が1.5℃を超える見込みと推測されており、とりわけ近年、気候変動に起因する被害が世界各地において頻発しています。こうしたことを背景として、「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)は、第7次評価報告書サイクルにおいて「気候変動と都市に関する特別報告書」の作成作業を開始しています。
OECCは、世界が脱炭素・持続可能な社会の実現に向けダイナミックな変革を遂げる中、国際社会からの期待に応えるべく、これまで培ってきた知見や専門性をフルに発揮して、幅広い分野において貢献するとともに、今後とも更なる研鑽を積み重ね、我が国の海外環境開発協力分野における中核的組織に相応しい役割を果たしてまいります。
メールマガジン「OECC LETTER」内の理事長メッセージは、以下からご覧いただけます。