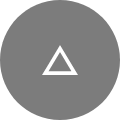PaSTIとは?ASEANの脱炭素に向けた「透明性」の土台を支える日本の国際イニシアティブ
PaSTI(Partnership to Strengthen Transparency for co-Innovation)は、環境省が主導する国際的な協力イニシアティブで、パリ協定に基づく各国の温室効果ガス(GHG)排出量の算定・報告・検証(MRV)体制の構築を支援することを目的としています。特にASEAN地域を中心に、制度設計、人材育成、算定ツールの導入、民間セクターの巻き込みなど、実践的な支援を幅広く展開してきました。
OECCは、PaSTIの実施支援機関として、政策対話の運営、研修の設計・実施、各国との協議・調整、試行事業の支援などを担ってきました。その中でも、2019年から2025年にかけて、日本ASEAN統合基金(JAIF)の支援を受けて実施されたのが「PaSTI-JAIF」プロジェクトです。最終フェーズとなるフェーズ3では、ASEAN加盟国を対象に、各国の制度整備と試行的な排出量算定の実施支援、民間企業との連携促進、地域全体の調和を目指したネットワークづくりなどが行われました。
最終ワークショップを東京で開催——6年間の成果と、次の挑戦へ
2025年7月1日・2日の2日間、OECCは本プロジェクトの最終ワークショップを東京都内にて開催しました。フェーズ3の成果を総括し、2030年以降を見据えた「調和の取れた透明性」の実現に向けた道筋を各国関係者とともに議論しました。
ASEAN加盟国の環境省・関連省庁の担当者、国際機関や金融セクターなど約40名が参加し、対面とオンラインを併用したハイブリッド形式で実施されました。
-1024x683.jpg)
Day1:制度整備とツール導入の成果を共有:活発な意見交換が展開

ワークショップ初日の前半は、ASEAN各国が自国で実施した試行的取り組みの成果を発表するセッションから始まりました。参加国は、それぞれの国情に応じた重点分野(廃棄物、工業プロセス、農業など)を選定し、PaSTIを通じてGHG排出量の算定や報告制度の試行を行ってきました。
各国の代表者からは、ツール導入の進展状況や、制度整備のステップ、関係機関や自治体、民間企業との連携事例が具体的に共有されました。特に、国境を越えた制度の比較可能性や、報告制度と法制度との整合に関心が集まり、質疑応答の時間は予定を大きく上回るほどの活発なやりとりが行われました。
午後のセッションでは、ディスカッションに先立ち、まずパリ協定下での透明性の強化に取り組む「透明性のための能力強化イニシアティブ(CBIT)」より、国家インベントリと民間事業者による算定報告の調和に関する講義が行われました。ここでは、各国が抱える技術的・制度的課題に対する国際的な支援の枠組みや、先進的な取り組みの事例が紹介されました。
続いて、三菱総合研究所からは、日本における温室効果ガス算定・報告・公表制度(SHK)の概要と、省エネ法・温対法・フロン法に基づく電子報告システム(EEGS)の運用実績が紹介され、制度横断的な電子的報告・管理体制について具体的な知見が共有されました。
さらに、アジア開発銀行研究所(ADBI)より、アジア地域における気候関連情報開示(例:TCFD等)と、それを促すための政策的・経済的インセンティブの動向についてのプレゼンテーションが行われました。
これらのインプットを踏まえて実施されたディスカッションでは、「民間セクターを巻き込んだ調和的透明性の実現」をテーマに、活発な意見交換が行われました。各国が直面する制度整備上の課題やデータの整合性の確保、インセンティブ設計の重要性など、現場レベルの具体的な論点が浮き彫りとなり、ASEAN地域全体で透明性フレームワークを調和させるための今後の方向性について、前向きな姿勢が確認されました。
Day2:脱炭素に向けた現場の取り組みと実践的学び~GHGガスの削減技術、都市の役割、民間の先進事例に焦点をあてて~

2日目は、GHGの算定・報告の「その先」にある、排出削減の具体的な取り組みに焦点をあてた視察プログラムが実施されました。
訪問先となったのは、神奈川県に位置する株式会社クレハ環境ウェステックかながわの廃棄物発電施設です。同施設では、産業廃棄物の収集から分別、焼却、そして発電に至るまでの一連の工程が見学できるよう整備されており、参加者は実際の現場を目の当たりにしながら、日本の技術と運用体制について理解を深めました。
この視察の一環として、近年ASEAN地域でも注目が高まっている都市における脱炭素の役割についても学習の機会が設けられました。具体的には、日本の脱炭素都市モデルである、川崎エコタウンの官民パートナーシップ事例が紹介され、行政と企業が連携して推進する脱炭素プロジェクトの仕組みや成果について解説が行われました。都市レベルでの実践的なアプローチに対し、参加者からは多くの質問が寄せられました。
また、視察プログラムの中では、アジア地域および日本におけるカーボンクレジット制度やサプライチェーンマネジメントに関する最新の取り組みも紹介されました。前日に続き、企業活動と排出量可視化の関係や、排出削減を促す経済的インセンティブ設計といったトピックへの関心は高く、積極的な質疑応答が続きました。
参加者にとってこの視察は、排出量の把握・報告にとどまらず、実際の削減行動につなげていくための知見を深める貴重な機会となりました。
フェーズ3の成果と今後の展望
PaSTI-JAIFフェーズ3では、制度構築、人材育成、民間との連携、地域間の情報共有といった多層的な取り組みがなされ、ASEAN地域の気候変動対応の基盤整備に大きく貢献しました。
本ワークショップでは、各国が直面する課題(例:予算不足、人材不足、データ連携の難しさ)とともに、今後取り組むべき方向性も明確になりました。特に、環境金融との接続や、各国のインベントリ制度と企業の算定制度の調和が今後の焦点となります。
OECCでは、今後もASEAN諸国の制度整備支援、ネットワーク形成、人材育成を通じて、地域レベルでの「調和された透明性」の実現に向けて支援を継続してまいります。

OECCのPaSTI事業をリードするマラビーニ主任研究員とトーマス研究員、
ランチ休憩中も議論が白熱。
PaSTIの活動を含む透明性向上支援事業紹介はこちら: