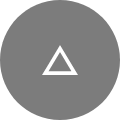特別企画 私の履歴書
OECCには、国際環境協力の最前線で豊かな経験を積んできた多彩な専門家が集まっています。本企画「私の履歴書」では、そうしたメンバーの歩みを通して、OECCの成り立ちと精神を紐解いていきます。
記念すべき第1回は、環境省で要職を歴任し、京都議定書交渉やJICA専門家としての海外協力など、日本の環境外交を支えてこられた竹本和彦理事長。その原点と情熱に迫ります。

OECC理事長 竹本 和彦
環境問題への関心の芽生えと環境庁への入庁
私が環境問題に関心を持ったのは、ちょうど大学に入学したばかりの1970年当初のことです。その時期、全国的に公害の波が押し寄せ、政府においては、こうした事態に対処すべく、環境庁(現在の環境省)が創設されました(1971年7月)。その後私は都市工学科に進学し、環境工学を学びました。時折しも1972年6月、ストックホルムで「国連人間環境会議」が開催されましたが、私たちの指導教官であった宇井純先生が水俣病患者の皆さんとともに、その国連会議に参加されていた様子が大きく扱われた報道に接し、環境問題に対する国際社会の関心の大きさをより身近なものとして受け止めていました。そんなこともあり、大学卒業後、環境庁に奉職することになりました(1974年)。
初めての国際会議と海外経験
環境庁に入庁したばかりの頃は、専ら国内の公害問題への対処が最優先課題であり、その当時、海外との接点といえば、パリに本部を置くOECDとナイロビに本部を置くUNEPが国際社会への窓口でした。また二国間協力としては、米国環境保護庁(EPA)との政策協議の場が設けられているのみでした。
そうした状況の中、1977年にパリで開催されたUNEP主催の「産業と環境」をテーマとする国際会議に私が派遣されることになりました。私にとって人生初の海外経験でもあり、パリに到着してからの一週間は文字通り、夢の様に過ぎていきました。またこの国際会議では、拙いながらも英語で発表する機会が与えられるなど激動の日々でした。この海外出張により、私自身の視野が広がったことはもちろんですが、それ以上に、それまでは頭の中のみで描いていた世界の国々から集った参加者の一人ひとりと直接に会話を交わし合うことがこれほど魅力的なことかと実感する毎日でもありました。この様に大きな衝撃を受けつつ、生の国際社会との触れ合いに魅了された私は、「将来は必ずや国際的な舞台で活躍できる仕事に携わりたい」との強い思いを抱いての帰国となりました。また同時に、英語力の乏しさを痛感し、今後は語学力向上に一層力を入れていこうと決意しました。
JICA専門家としてのマレーシア赴任
その後、世の中も徐々に環境問題に対する国際的対応が求められ、私にもJICA専門家としてMalaysiaへの赴任の機会が巡ってきました(1987年)。その頃は途上国においても、都市化や経済活動の急速な進展に伴い、環境汚染問題が深刻になっていました。そうした中、タイ、インドネシア、マレーシアの各国での環境分野における協力ニーズを把握するため、JICAと環境省が協力して調査団が派遣されました(団長:橋本道夫筑波大学教授、後にOECC初代理事長)。この調査団報告を踏まえ環境庁は、同庁職員をこれら3ケ国に政策アドバイザーとして直接派遣することを決定しました。
私はその一環で、1987年1月より、マレーシアに環境技術研修計画の策定のための専門家として、3ケ月派遣されることになりました。限られた赴任期間ではありましたが、着任当初から各地の地方環境事務所を精力的に巡り、環境業務の現場におけるトレーニングニーズの特定に努めました。また現地調査の合間を縫って開催された関係省庁局長会儀では、環境局の担当局長と共に現地調査の中間報告や研修計画策定方針などについて説明を行いましたが、この会議での議論は、最終的に報告書をまとめるうえで大いに役立つことになりました。
最終的に、地方環境事務所での業務に携わる技術職員を対象とした研修計画を盛り込んだ報告書をとりまとめ、提出することが出来ました(写真1)。お陰様にて、この最終報告書は、カウンターパートの環境局はもとより、国全体の国際協力案件を統括する「経済計画ユニット」(EPU)の担当者からも高い評価を頂けたのは法外の喜びでありました。

写真 1:報告書を提出する竹本理事長
再度のマレーシア赴任と研修実施
こうしたことを受けて、マレーシア側では、せっかく立派な研修計画が策定されたので、次年度はこれを実施に移したい、ついては日本から再度専門家を派遣してほしい旨の要請がありました。この要請を踏まえ日本側で検討した結果、再度私が専門家として翌年赴任することになりました。
当時私は、大気保全局においてNOx総量規制の担当補佐として政令改正作業に取り掛かっており、私が派遣されることになると、3週間近くそのポジションが空席になることから、局内ではそれが可能かについての議論がありました。幸いにも、上司の課長はじめ局内幹部の理解を頂き、私の派遣が叶うことになりました。
1988年2月末、再度クアラルンプールの空港に降り立った私は、灼熱の太陽の光を浴びながら昂揚感がみなぎっていました。そしていよいよ2年目の赴任として初めて環境局のオフィスに出勤したところ、担当部局の職員はもとより、前回の派遣時に知り合った多くの同僚が、次々に歓迎の言葉をかけに来てくれたのです。その時の嬉しさと感動は、旧同僚に再会できた喜びと同時に、国際協力に再び携わることが出来た実感とが交錯していたように思われます。
その後、最初の一週間で研修の講師やField Visitの訪問先との打合せなどを整え、2週目には研修の実施、そして3週目の前半は研修のレビューという感じで、大変慌ただしい期間ではありましたが、関係する部署の職員や専門家の皆さんは既に旧知の仲だったこともあり、何事も大変スムーズに進行することが出来ました(写真2)。
それにつけても、この限られた期間に環境局の職員が目的を共有し、協力してくれたこと、本研修プログラムの実施を通じて職員との絆が一層培われ友情の輪が次々に広がっていったことを実感し、改めて海外環境協力の醍醐味を肌で感じることが出来ました。こうした経験が、その後、様々な海外協力の活動に継続して従事していく原動力となったと確信しています。

写真2:研修時のGroup Discussionの様子
海外環境協力への継続的な関与
その後、私の職業人生は世界銀行やIIASA(ウィーン)への派遣などへとつながり、国際社会が脱炭素・持続可能な社会実現に向けて大きくシフトしていく潮流に乗って、海外環境開発協力の世界にのめり込んでいくことになりました。