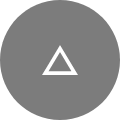OECCは2025年7月、ジャガイモの原産国とされているペルーで開催された国際条約「食料と農業のための植物遺伝資源に関する国際条約(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture:ITPGR)」の第14回作業部会に、日本政府代表団の一員として参加しました。OECCはアジアの一員として作業部会のメンバーを務める農林水産省担当官の国際交渉を支援し、先進国と開発途上国、さらには産業界などとの橋渡しに貢献しました。
気候変動にレジリエントな品種改良作りにも貢献する植物遺伝資源の保全と持続可能な利用
植物遺伝資源とは、農業や食料生産に役立つ「遺伝子の宝庫」ともいえる存在です。例えば、病気に強いジャガイモや、暑さに強い稲の品種。その背後には、世界中の多様な植物から受け継がれた遺伝子があります。
近年、気候変動の影響が農業・生産にまで及び、暑さで生育が阻害されるだけでなく、農作物が病気にかかりやすくなるなど、収量の低下が懸念されています。そのため、種苗企業や大学・研究機関では、病気への抵抗性を高めるための品種改良が進められており、その基礎となる病気に罹りにくい遺伝子を持つ植物遺伝資源の探索が行われています。
しかし、開発による土地利用の変化などにより、貴重な植物遺伝資源が失われつつあります。こうした背景から、国際的に植物遺伝資源を保全しつつ、持続可能に利用するための枠組みとして、ITPGRが採択されました。


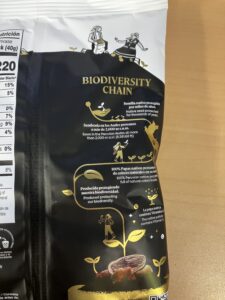
国際交渉における進捗
ITPGRは、植物遺伝資源・種子を保全し持続可能に利用するための国際協力を促進する条約として、2003年に発効しました。日本では農林水産省が主務官庁として担当し、農研機構や種苗業界などと協力しながら円滑な実施を進めています。
第14回作業部会では、植物遺伝資源や種子の取引・移動を円滑に行うための仕組みの見直しが議論されました。依然として北米・欧州の先進国とアジア・南米・アフリカの開発途上国の間には意見の隔たりが見られましたが、各国代表者は妥協点を探るため非公式協議を進めています。

OECCの役割
OECCは、遺伝資源や遺伝的配列データ管理に関する法律や政策の分野で高い専門性を有しています。今回の作業部会では、これまでに培った知見と経験を活かし、各国代表との意見交換を通じて情報収集を実施しました。
また、各国の発言内容を丁寧に把握し、政府内での円滑な情報共有に努めました。OECCの参加は、先進国と開発途上国の間に立ち、建設的な対話の促進に寄与する貴重な機会となりました。

今後の展望
第14回作業部会での条約改正を含む交渉テキストは、2025年11月末に同じくペルーで開催される第11回理事会(COPに相当)で最終的な結論が出される予定です。2019年には一度交渉が決裂しており、今回はその再挑戦となります。
米国も参加するこの枠組みが、多国間主義と国際協力を維持・強化できるか、世界的な注目が集まっています。OECCとしても、今後の展開を注視しつつ、12月に改めて活動報告をお届けする予定です。